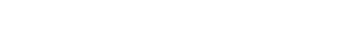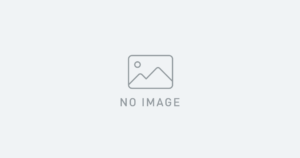こんにちは。
セールスコピーライティング普及協会認定ライターの中岡です。
黒いタートルネックでプレゼンする経営者といえば恐らく、この方を想像するかと思います。
2011年に56歳という若さでこの世を去ったAppleの元最高経営責任者、スティーブ・ジョブズ。
彼がいざプレゼンをすると、まるで魔法にかかったかのように、観客は新製品に魅力を感じ、既存製品への不満を忘れ、高額な価格にも納得し、聞き入ってしまいます。
その様子をAppleの元社員達は「現実歪曲フィールド(Reality Distortion Field)が発生する」と言っていたようです。
これは、想像力をかきたてて、イマジネーションの世界に引き込み、聞く者を感動させてしまう…そうしたジョブズ氏のカリスマ性を表現した言葉。
では、この魔法のようなプレゼンはジョブズ氏だからできたのでしょうか?
黒いタートルネック、価値観の共有、称賛を織り交ぜた語りかけ、壮大な使命感、洗練された会場演出。
実は、これらは「好意の法則」という心理学を駆使したもので、高額商品の提案やセールスに活かせる誰にでもできるテクニックなんです。
そこで今回は、ジョブズ氏も活用した、好意の法則に関する5つのポイントをお伝えします。
服装を軽視する講師は売れない

面白く話せるし、伝える内容も有料級で実践的なものばかり…でもなぜか商品・セールスの成約に繋がらない。
そういったお悩みがある方は、信頼できる専門家としての印象を与えることができていないかもしれません。
アルバート・メラビアンが提唱したメラビアンの法則によると、人とのコミュニケーションは、視覚情報55%、聴覚情報38%、言語情報7%のウェイトで影響するとされています。
それだけでなく、プリンストン大学のアレクサンダー・トドロフ心理学教授は著書「第一印象の科学」で、知らない人の見た目の印象を判断するのに、0.1秒あれば必要な情報は揃うと書いています。
つまり、講師が壇上に上がるまでの数秒で、参加者のほとんどは、服装やしぐさなどから、その人の印象を決めてしまうということ。
それだけ、講師にとって外見というのは重要な要素なのです。
たとえば医者は常に白衣を着て仕事するのが普通ですが、もし短パンにビーチサンダルスタイルの医者がいたとしましょう。
そんな医者に診てもらいたい人なんているでしょうか?信頼できるでしょうか?
恐らく嫌な方が大半でしょうし、たとえ権威性のある先生でも言われた言葉を信用できません。
成功している講師の多くは、「紺色のスーツ」「白い白衣」「スリーピーススーツ」など、自分なりの制服を持ち、スタイルを確立しています。
金融機関など仕事内容が堅めなら格式高いスーツ、ベンチャー企業向けならややカジュアルに、というように参加者が親近感を持てる装いを心掛けなければいけません。
毎回黒いタートルネックで統一していたジョブズ氏は、IT業界でウケのいい服装で、かつ同じスタイルでの演出は印象付けのための服装でした。
セミナーの内容や商談のトークが充実しているのに、思った以上に成果が上がらない理由には服装の軽視が一因にあるかもしれません。
参加者に共感させ結束力を高める

人は本能的に自分と似た人を仲間だと認識し、信頼を寄せる傾向があります。
これは心理学で「類似性の法則」とも言われ、生存するためには、味方を素早く識別する必要があるという、人類の本能に根ざして身に付いたもの。
この類似性は単一の要素ではなく、主に4つのポイントで構築されます。
①属性の類似性
出身地、年代、役職、会社規模など、表面的な情報から親近感を与えること。
②体験の類似性
業界特有の課題、経営者特有の孤独感、成長段階での共通の悩みなど、参加者が「まさに自分と同じ」と感じる体験を共有すること。
③知識レベルの類似性
参加者の理解度に合わせた専門用語の使用や、業界の常識を前提とした話し方をして、「この人は我々のレベルを理解している」という印象を与えること。
④価値観の類似性
「家族を大切にしたい」「会社の未来を真剣に考えている」など、参加者が共感できる価値観を自然に開示すること。
これらの類似性はセミナーの進行に合わせて、徐々に共通点を明かすことで、共感を生みやすくなります。
冒頭では属性など軽い話の共通点から入り、本格的な内容を伝える前に体験や知識レベルの共通点、クロージング前に価値観の一致を示す、という段階的なアプローチが参加者の心を徐々に開いていきます。
更に、参加者の言葉遣い、話すペース、身振り手振りなどを自然に真似ることで、無意識に親近感を与えることが可能。
たとえば、関西在住の参加者が多ければ、関西弁や関西のイントネーションを取り入れ、IT業界なら横文字を多用するなど、相手に合わせて調整するのです。
ただし、過度な類似性アピールは疑念を生むため要注意。
明らかに作られた共通点は不信感を招き、表面的すぎる共感は「この人は本当に理解しているのか?」と思わせてしまうためです。
質問した人を褒めて雰囲気を盛り上げる

セミナーでは何かしら質問の機会があるでしょうが、その際の対応によって、会場の雰囲気を大きく変えることができます。
たとえば、回答する際「良い質問ですね」と答える講師と、「○○の視点で質問できるなんて、さすが○○業界の方ですね」と具体的に褒める講師では、会場の雰囲気が全く異なるもの。
後者の場合、質問した人は満足げな表情になり、他の参加者も「自分も質問してみよう」という積極的な雰囲気となるのです。
また、その際に質問者への称賛パターンをいくつか準備しておくと効果的。
「その視点は私も気づきませんでした、勉強になります」「○○業界ならではの鋭い質問ですね」「今日一番本質的な質問をいただきました」など、質問の内容や質問者の背景に合わせて具体的に褒めることで、特別感を演出。
「皆さんのレベルが高いので、普段は話さない上級テクニックもお伝えします」「この業界の方々だからこそ理解していただける内容です」など、参加者全体を持ち上げることで、会場全体の自己肯定感を高めることもできます。
特にお薦めなのは休憩時間の個別対応で「先ほどの質問、とても良いポイントでしたね」「○○の取り組み、素晴らしいですね」と直接声をかけることで、その人にとって忘れられない体験になります。
人は褒められると、その承認欲求から褒めてくれた人への好意度が大きく高まるもの。
ただし、称賛の質については注意すべきで「すごいですね」と淡白な発言ばかりを連発していても逆効果。
具体的で的確な称賛でなければ、返って信頼を失うことになるので要注意です。
一緒に業界を変えましょう!の威力

以前、テレビにもよく出演される著名な方のセミナーに参加した際、とても印象に残ったメッセージがありました。
私が普段携わっている宝飾品業界向けのセミナーだったのですが、講師が「このままでは日本の宝飾品業界の技術は海外に負けてしまいます。でも、今日お集まりの皆さんなら、まだ業界を変えることはできます!」といった話をされました。
それまで競合同士だった同業の参加者達が情報交換を始め、「一緒に勉強会をしませんか」といった声が上がり、結束が高まったのです。
これは、対立していたグループ同士が、共通の目標を持った瞬間に協力関係になるという心理を活用したもの。
ロバーズ・ケーブという実験で実証されているもので、これをセミナーでも応用したのでした。
古い業界慣行・海外企業の脅威・時代遅れの経営手法など、参加者が共感できる共通の敵を明確にし、設定することで、自然と結束感が生まれます。
この度のメッセージを通して、個々の会社の問題を「業界全体の問題」として昇華させ、「みんなで解決しなければ」という使命感を醸成したのでした。
こうした雰囲気作りは、グループワークなどで協力体験を創出することでも可能。
「隣の方と意見交換してください」「チームで解決策を考えてみましょう」など、参加者同士が協力する体験を意図的に作ることで、講師への好意も高まります。
成功事例のシェアでは、「○○さんの成功事例をみんなで学びましょう」「成功している方々のノウハウを共有しませんか」という形で、参加者同士の学び合いを促進します。
「一人では難しいことも、みんなで取り組めば可能になります」という流れで、自然に継続サポートやコミュニティ参加の必要性を感じさせ、商品・サービスへの成約に繋げることができるでしょう。
投資意識を上げる会場の演出

同じ内容のセミナーであっても、駅前の貸会議室と市内の高級ホテルと開催場所の違いで、印象は大きく変わります。
これは参加者が無意識のうちに「この環境にふさわしい価格」を想定するため。
この心理メカニズムにおいて、会場の格と商品価格の連動は基本中の基本。
10万円の商品なら中級ホテル、100万円の商品なら高級ホテルというように、商品価格に見合った会場選択が重要。
また、会場だけでなく、クラシック音楽のBGM、適度な照明、高品質な資料など、五感で感じる要素全てが商品の価値認識に影響します。
手触りの良い紙質、重厚感のある製本、美しいデザインなど、「安っぽくない」印象を与える工夫が、商品価値の認識を高めます。
こうした雰囲気作りは受付からでなく、もっと前の段階である、会場の選定自体が重要。
一般的な会議室との差別化を明確にすることで、提供するサービスの価値も高く認識されます。
会場確認から着席までの動線で、参加者が「特別な体験をしている」と感じる仕掛けをすることで、参加者の投資意識を更に高めるのです。
まとめ
今回はスティーブ・ジョブズが活用していた好意の法則について、説明しました。
これらのテクニックは単独で使うものでなく、統合的に活用することで、効果が相乗的に高まります。
外見で信頼感を与え、類似性で親近感を醸成し、称賛で特別感を演出し、使命感を共有し、価値を高める。
この流れが自然に作られた時、参加者は「この人から学びたい」「この人と一緒に成長したい」と感じるようになり、商品・サービスの成約率を底上げすることが可能となります。
好意という土台ができていることで、見込み客との関係性が構築できます。
これこそが、ジョブズが製品発表会で見せていた「現実歪曲フィールド」の正体だったのではないでしょうか。
ぜひ、今回お伝えした内容を実践いただき、あなたのセールスにおいて少しでも成約率が高まることができれば幸いです。
当協会では今回お伝えした内容のような、セミナー説明会型セールスの極意を無料公開しております。
成約率100%を実際に叩き出したスライドの解説動画3本を無料でプレゼントしておりますので、こちらのページから登録くださいませ。
最後までご覧頂き、ありがとうございました。